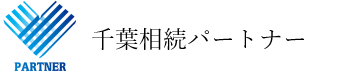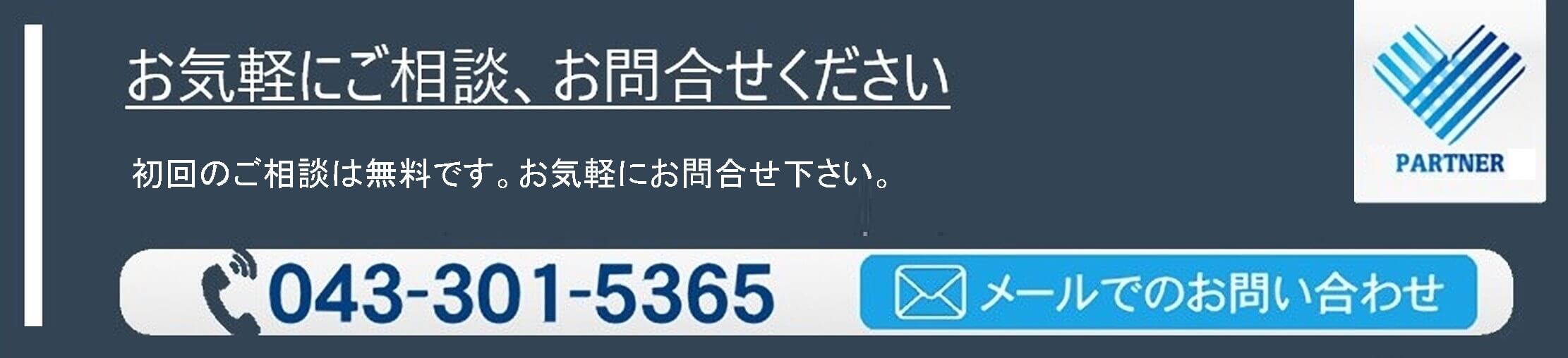相続お役立ち情報
相続に関わる用語を記載しております。
遺言
被相続人が生きてる間に自分の意思を示すもの。財産を誰にどのくらい渡すかを伝えるもの。
遺産分割協議書
遺産分割協議とは相続人全員で遺産の分け方を決める話し合いですが、その内容を書面におこしたものを遺産分割協議書といいます。※遺言状がある場合は、原則遺言状に従って相続することになります。
遺留分
一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない一定割合の遺産のことをいいます。法定相続人とは異なり、「配偶者」「子」「親」の直系卑属、直系尊属のみ対象です。不公平な遺贈、贈与があった場合に遺留分の割合に基づき遺留分侵害請求ができます。
換価分割
相続した資産等を売却して現金化し、その現金を相続人で分ける方法です
葬儀に関する費用控除
相続税の計算は、相続人が負担した葬式費用を遺産総額から差し引きすることができます。差し引きできる費用は通常以下のようなものです。
・火葬や埋葬、納骨のための費用
・遺体や遺骨の回送にかかった費用
・葬式前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用。お通夜など。
・お寺などに対しての読経料のお礼差し引きできないものとしては以下のようなものがあります。
・香典返しの費用
・墓石や墓地にかかった費用
・初七日や法事の費用
相続放棄
被相続人の全ての財産(プラスとマイナス)を相続せずに放棄すること。借金や未払金、債務などが多額の場合に相続放棄することで一切借金を引き継がない様に出来ます。放棄する場合、相続開始から3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。また、相続財産に手を付けてしまっている場合放棄が認められなくなります。
代襲相続
被相続人より先に相続人が亡くなっている場合に、被相続人から見て「孫」「甥、姪」などが財産を相続することをいいます。代襲相続人は本来の相続人と同じ相続割合を持ちます。
二次相続
夫婦のどちらかが亡くなった際を一次相続、その後配偶者が亡くなった際を二次相続といいます。一次相続で相続税が最小になるようにしたとしても、二次相続の際にかえって相続税の負担が大きくなることもあるので、慎重に考える必要があります。
準確定申告
亡くなった方の所得に対して行われる確定申告を準確定申告といいます。申告の義務は相続人となっています。
小規模宅地の特例
被相続人の自宅や事業に使用していた宅地等について、一定の基準を満たした場合に評価額を軽減できる特例
相続時精算課税制度
受贈者(子や孫)が2,500万円まで非課税で贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった時にその贈与財産を相続時の財産と合計して相続税を計算し、納税する制度
相続税の基礎控除額
相続税を計算する上で一定額差引することができるようになっており、3,000万円+(600万円×法定相続人数)で計算されます。
贈与税の基礎控除額
贈与税を計算する上で一定額差引することができるようになっており、毎年110万円を差引することができます。
相続放棄
相続が発生した際に、財産や債務を一切相続しないこと
代襲相続人
本来相続人となるはずだった方が、死亡や相続欠格等があった場合にその代わりに相続する人(子供や兄弟等)のこと
二次相続
夫婦の一方が亡くなり相続が発生後、更にその後配偶者が亡くなり相続が発生した際の相続のこと
被相続人
亡くなった人のこと
法定相続人
配偶者、直系卑属(子や孫、ひ孫など)、直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母など)、兄弟姉妹(亡くなっている場合には甥姪)などのこと
法定相続分
法定相続人が2名以上いる場合の各人の相続割合のこと
路線価
道路に面した標準的な宅地の1平方メートルあたりの評価額のこと。土地の相続税評価額を求める際に用いることがあります
エンディングノート
自分に万が一のことがあった場合に備えて、自分に関する様々な情報をまとめておくノート