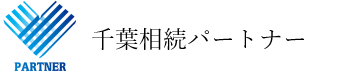相続関係のQ&Aを記載しております。
事務所に伺うことが難しいのですが、他に方法はありますか。
お電話、メール、ZOOM等のオンライン面談も可能でございます。またご希望の方は有償になってしまいますが、ご訪問することも可能です。
平日に休みを取るのが難しく、土日祝に面談したい。
会社員のため平日に時間を取ることが難しいかたは沢山いらっしゃいます。このような場合でも日程を調整してご面談することは可能ですので、お気軽にお申しつけ下さい。
遺産分割が揉めそうなのですが・・
トラブルが予想される場合は弁護士と連携して対応を進めさせていただきますのでご安心ください。
準確定申告とは何でしょうか。
お亡くなりになられた方が、生前事業や不動産収入を得て確定申告をしていた方の場合、1月1日~お亡くなりになった日までの分を確定申告することを準確定申告といいます。※相続とは異なり、亡くなった日から4カ月以内に申告が必要となっています。
以前相続税を申告したが、正しく申告できているか不安です。
相続税は不動産や有価証券など複雑な評価を用いて行うため、判定方法やとらえ方によって大きく変わることがあります。正しく計算しなおすことで、納税額が過大であった場合は還付することが可能な場合がございます。不安な点があれば、お気軽にお問合せください。
長年の付き合いがある顧問税理士がいるのですが、相続税は苦手そうです。相続税だけ依頼したいのですが可能でしょうか。
もちろん可能です。通常の税理士であれば、相続税は対応していないというのも珍しくありません。弊社は相続税を得意とする税理士が対応致しますのでお気軽にお問合せください。
独身で相続人がいない場合どうなるのでしょうか。
法定相続人がいない方の財産は、遺言が無い限り最終的に国庫帰属となります。
法定相続人ではない者が遺言で遺産を受け取った場合でも相続税は発生しますか。
相続税は、財産を取得したものが納税義務者となるので、法定相続人でなくとも納税義務が生じます
遺留分とはなんでしょうか。
遺言で財産を誰にどのくらい相続させるか指定はできますが、特定の方へ集中してしまうことがないように、法定相続人に最低限保障される取得分のことをいいます。遺留分の割合は誰が相続人になるかで異なります。
相続人が複数名いるのですが、それぞれ申告をすることができますか。
相続人各人がそれぞれ申告することは可能です。ただし記載されてる内容、金額等が異なっていたりすると税務調査のきっかけとなることが考えられます。実務上は相続人代表を決めて、連名で被相続人の住所地管轄の税務署に提出することが通常となっています。
アパートを建てると相続税対策になると聞いたのですが。
アパートなど人に貸すことを目的としたものは、自用地(自分で使用する土地)と比べて財産評価額が低くなります。また、アパートを建てる際に金融機関から借入をした場合、相続財産から債務として控除することができるため、相続税を少なくなります。ただし相続した方は債務も引き継ぐことになりますので、将来的に問題なく返済していけるかもしっかりと検討が必要です。
名義預金とはなんですか。
親が子供名義で通帳を作り、口座の入出金等の管理を親が行っている場合、実質親のものとして扱われてしまいます。その場合相続財産として課税されてしまいます。