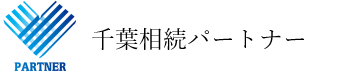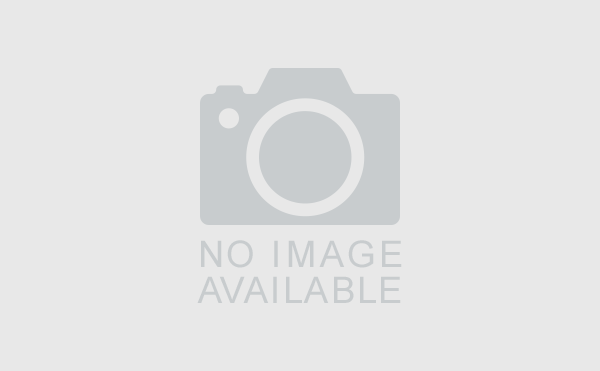2025年以降の相続税申告で注意したい小規模宅地等の特例の要件
相続税の申告で多くのご家庭が活用しているのが「小規模宅地等の特例」です。
居住用や事業用の宅地を相続する際に、土地の評価額を最大80%まで減額できる強力な節税制度で、相続税対策の柱といえます。
しかし、2025年以降はライフスタイルの変化や制度解釈の厳格化により、従来は適用できたはずのケースでも特例が使えない可能性が増えています。
小規模宅地等の特例で注意すべきポイント
1. 「同居」要件の厳格化
被相続人が居住していた自宅について特例を受けるには、相続人が同居していることが原則条件です。
しかし実際には、子ども世帯が別居している、転勤などで同居できなかった。といったケースが増えており、特例の適用が難しくなっています。
2. 「生計一」の判定
同居していなくても、生活費の援助などにより「生計を一にしていた」と認められる場合は適用が可能です。
ただし、実際には銀行口座の資金の流れや生活実態を証明する資料が必要になることも多く、専門的な判断が欠かせません。
3. 持ち家の有無
同居していた相続人であっても、既に自分名義の自宅を所有している場合には、特例が適用できないケースがあります。特に都市部のご家庭では注意が必要です。
2025年問題で高齢化や核家族化により、親と子が別居している。同居していても子は既に自宅を所有しているといった事例が増加しています。
この結果、小規模宅地等の特例が利用できず、相続税負担が大きくなるケースが今後さらに増えると予想されます。
小規模宅地等の特例は強力な節税制度ですが、要件を満たさなければ一切の適用が受けられません。
特に「同居」「生計一」「持ち家の有無」は実務上の重要ポイントです。
千葉相続パートナーでは、お客様ごとの状況に合わせた最適な相続対策をご提案しております。
「うちの場合は特例が使えるのか?」「今から準備できることは?」といったご相談も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。